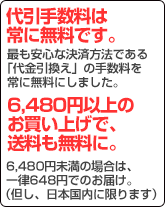2005/04/13
3.神の存在
神の存在
「私にとって、神は、川の流れであり、吹く風であり、流れる雲ですね……」
妻は暫く考えてこう言った。
日本文学の古典、方丈記の冒頭の文章を、私は思い出した
。
----ゆく河の流れは絶えずして、もとの水にあらず、よどみに浮かぶうたかたには、かつ消え、かつ結びて、久しくとどまりたる例なし……。
生命が、この地球に誕生しておよそ30億年というが、大きな自然の流れのなかで、今日もこの生命は続いている。生と死は常に繰り返されており、そこに自然があり、そこに神の存在をみる。川の流れや、流れる雲に神の存在をみるという妻の発言は、ごく当然のことだ。
細胞の小器官の一つにミトコンドリアがある。その働きは、酸素を消費して、呼吸基質を分解する好気呼吸の反応を担っているのだが、父由来の要素は全くなく、遺伝の優劣関係も生じない。
私たちのミトコンドリアが母親由来そのものであり、それはそのまま、母方の祖母のミトコンドリアに遠く繋がっている。
このようなことから、私たち現代人の祖先は、およそ17万年前のアフリカの一女性に行き着くという。その女性が私たちの最初の母であるということになる。そこで、この女性をミトコンドリア・イヴと名づけている。
この生命は、大きくみれば、一つの点と線の流れのなかで、しっかりととらえることができる。
先日、比叡山の峰々を一日30キロ走り回って礼拝する、もっとも苛酷な修行僧を追ったテレビ番組をみた。
飛ぶように、けもの道のような山路を走り回る修行僧の姿がそこにあった。
「崖に落ちないように気をつけている。しかし、万一、落ちたら死です。当然のことです……」
修行僧は、テレビのなかで、明るく答えていた。
「もし死んだら、枯葉や多くの樹木、そして動物のために、私の死体が他の生命体のための養分となります。私個人の死が他者の再生のための契機となることを信じています」
死は生の始まりでもある。
山修山学。12年間、俗界を離れて山に籠り、仏法を学ぶべきだという伝教大師、最澄の教えだ。そのため、比叡山で千日回峰行をはじめ、修行地獄といわれる厳しい修行の日々が行われている。
この修行僧にとって、死は自然のサイクルの一点にしか過ぎないのである。
また、最近、梅原猛暑の「仏教」(朝日新聞社刊)を手にした。
この記述のなかに、西洋の聖者は殺され、釈迦は静かに死につくとある。釈迦の人生の姿が、いちばんはっきり表わされているのが涅槃の姿であるという。
釈迦の死は、全ての人間は死ぬ。生きとし生けるものは全て死ぬ。
その死の真理を人々に知らせるために、安らかな死につくという、実に静かな死であったと述べている。
そして釈迦は天国のことを説かない。人生はこういうものだと言って、静かに死んでいったとある。
紀元前五世紀の時代に存在した釈迦は、時間と存在を実存としてとらえ、人間に限らず、全てのものは時間の流れのなかで変遷していく、それが生であり、死であるという偉大な哲学を私たちに贈ってくれた。
病者と存在
病むとき、その病の大小に限らず心を病むものだ。それが病者である。
治る見込のない難病など、死を意識せざるを得ない病者は、心が不安定となり、心と心が通じあう医師と出会ったとしても、温かい家族に恵まれていたとしても、病者の本質は、たえずやってくる孤独感のなかで生きねばならない。孤独と孤独感は別だ。
病んでみて、生きるということが、いかに物質面を超え、精神の世界そのものであるかを実感する。病者は一人で歩む実存的存在なのだ。
生きることについて、その苦悩をドストエフスキーは、こう述べている。(ゼンタ・マウリーナ著、「ドストエフスキー」紀伊國屋書店刊)
それは地獄とは何かという問に対して、こう答えている。
----愛することがもはや出来ないという苦しい意識だ。愛してくれる人をひとりも持たなかったら人生は悲しい。われわれの愛に、だれも答えてくれる者がいなければ、われわれは絶望する。
さらに、愛する能力を失ったいうことを
----われわれの心に愛の感情を呼びさますことができないという意識を持つならば、われわれはすでに死んでいるのだ。
神は遠くにあって、われわれの心には地獄が燃えている。
なぜならば、愛して神に近づくかぎりにおいてのみ、われわれは生きているからだ----と。
今日の社会は、金が全てを支配した物質的競争社会である。神は遠くに押しやられてしまっている。
病者にとって、社会保障制度は生活するための重要な命綱である。この生活基盤があって、流れる雲、吹く風、路傍に咲く名もない花の美しさを感じるのである。生きるということは、心の面も含めて、この現実そのものの実体を愛することが第一だ。
そして人はさらに自分自身の歩むべき道を哲学的に心のなかに強く刻み込んだときその決断によって生への意欲が、自分自身では意識しなくても、強くなるのではないか。その静かなる情熱には死は入り込めないだろう。私はそう思う。
間違っても生と死の場を提供する医療の世界にイヴァン・イリッチが危惧(脱病院化社会)するような医療システムを構築してはならない。
1929年生まれの、自然科学、神学、歴史学と幅広い社会学者、イヴァン・イリッチは、現代の医療体制は「患者」生産工場と化し、人間の誕生から死までを、技術管理下におくことに反対している。
その内容をみると----患者は常日頃から自律性を持って、医師と対等に語り合い、人としての医療のあり方を主張している。
現代社会において生活のあらゆる側面が医療化され、かつ管理され、医療が一種の「禁断症状」となり、医療から遠ざけられると耐えがたい不安と苦痛を起こす。そこに医療を大量に消費する構造ができあがり、これによって健康は収奪される。
この医療化が進むと、人々は自主的な健康への判断や行動を放棄して、ひたすら医療に対して依存的になる。この結果、広く、かつ深く接するべき病苦や死の主体的意味を失わせてしまう----と、この論文は主張している。病苦や死を、ただ厭なもの、恐ろしいものとして生の本質を見失うと述べている。
今日、医療改革がなされているが、情報開示だけではなく、病者も医療に参画して、人として、仲間として、どう医療を創るか。そのことによって死の残酷性はなくなる----そう思う。
生と死を大きな自然の流れのなかでとらえて、日々を送ることの大切さが、そこにある…。(おわり)
マルチタイプ ミネラル |
セットタイプ 話題の栄養素 |
ビタミン |

サプリメント通販ホーム サプリメント一覧 健康情報を見る
送料・ポイント案内 よくある質問・お問合せ 会社概要
c 2005 A'prime, All Rights Reserved. Tel: 043-279-1708 Fax: 043-278-7004 Privacy